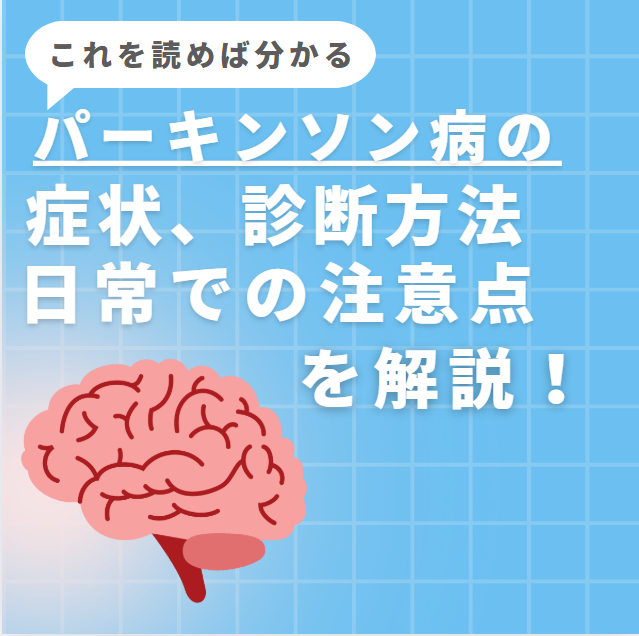パーキンソン病は、高齢者に多く見られる病気で、日本では約16万人が罹患していると推定されています。この病気は、脳内の特定の神経細胞が少しずつ減少することで起こり、主に体を動かす能力に影響を与えます。
症状の特徴
パーキンソン病の主な症状は以下の4つです。
- 振戦(しんせん)
- 手足が震える症状で、特に安静時に目立ちます。
- 筋固縮(きんこしゅく)
- 筋肉が固くなり、動きがぎこちなくなります。
- 無動(むどう)・寡動(かどう)
- 動き出しに時間がかかったり、全体的に動作が遅くなります。
- 姿勢反射障害(しせいはんしゃしょうがい)
- バランスが取りづらくなり、転倒しやすくなります。
これらの症状は、個人差があり、初期段階では気づきにくいこともあります。またパーキンソン病は進行性疾患のため病気が進行するにつれ、上記の症状が強く出現したり、他の症状(幻覚、精神症状、不眠等)が出現する可能性があります。
原因は?
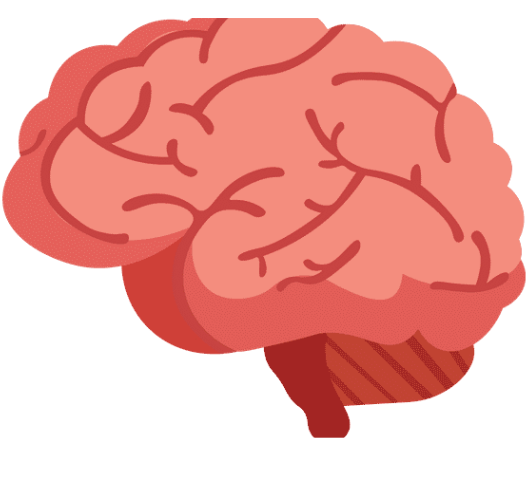
パーキンソン病の主な原因は、脳内の**黒質(こくしつ)**という部位でドーパミンという神経伝達物質を分泌する細胞が減少することです。ドーパミンは、筋肉の動きを調整し、体をスムーズに動かす役割を担っています。しかし、なぜこれらの細胞が減少するのか、正確な原因はまだ分かっていません。
遺伝的要因(家族内の発症例)や環境的要因(特定の農薬や毒素への曝露など)が関与していると考えられていますが、ほとんどのケースでは遺伝の影響は小さいとされています。
診断方法

パーキンソン病の診断は、主に医師の問診と身体診察によります。具体的には、以下の点が確認されます。
- 症状の有無や進行具合
- MRIやCTスキャンなどの画像検査(ただし、他の疾患を除外するための補助的なもの)
- ドーパミンの減少を確認する特殊な検査(DATスキャンなど)
治療法
現在の医学では、パーキンソン病を根本的に治す治療法はありません。しかし、症状をコントロールすることで、生活の質を向上させることが可能です。
薬物療法
- レボドパ
- この薬は、体内でドーパミンに変わる物質を補充するものです。ドーパミンが不足すると筋肉の動きがスムーズでなくなるため、この薬を使うことで日常の動作がしやすくなります。
- ドーパミン作動薬
- ドーパミンの働きを補助する薬です。
- MAO-B阻害薬
- ドーパミンを分解する酵素の働きを抑えます。
これらの薬は、症状に合わせて医師が適切な組み合わせを処方します。
リハビリテーション
運動療法や理学療法を取り入れることで、筋力やバランス能力を維持します。専門家の指導のもと、日常生活での動作がしやすくなるようサポートします。
外科的治療
薬物療法で十分な効果が得られない場合には、脳深部刺激療法(DBS)が選択肢になることもあります。これは、脳の特定の部位に電極を埋め込み、電気刺激を与えることで症状を軽減する治療法です。
日常生活での注意点

パーキンソン病の患者さんが安心して生活を送るためには、以下の点が重要です。
- 転倒を防ぐ環境づくり
- 家の中の段差をなくし、滑りにくい床材を選びます。
- 廊下や階段に手すりを設置します。
- 部屋の明かりを明るく保ち、夜間の移動時には足元灯を使います。
- カーペットやコード類を片付け、つまずきやすいものを排除します。
- 狭いところでは足が出にくくなるため、床に物を置かないようにしましょう。
- 適度な運動
- ウォーキングやストレッチを日課にすることで、体の柔軟性を保ちます。
- パーキンソン病は体を捻る、伸ばす運動が硬くなる傾向にあります。
- 体が硬くなるのを防ぐためストレッチを定期的に行いましょう。
- 首の筋肉も硬くなり飲み込みやずらさや大きな声を発することが難しくなります。そのため肩や首周りのストレッチを行いましょう。
- バランスの取れた食事
- 薬の効果を最大限に引き出すため、医師や栄養士のアドバイスに従った食事を心がけます。
家族や周囲のサポート
パーキンソン病の患者さんにとって、家族や周囲の理解とサポートが何よりも大切です。
- コミュニケーションを大切に
- 病気の進行や不安について話し合う場を設けます。
- 専門家に相談
- 医師やケアマネージャーに相談し、必要なサービスを受けられるようにします。
- 介護者の負担軽減
- 地域の支援サービスやデイケアを活用しましょう。
まとめ
パーキンソン病は早期に診断し、適切な治療と生活の工夫をすることで、症状をコントロールしながら日常生活を充実させることができます。病気についての理解を深め、患者さんやその家族が前向きに生活を送れるよう、周囲も協力していくことが大切です。
自分の周りにパーキンソン病の方がいる、自分がパーキンソン病でどこに相談したらよいか分からない、どんな運動をした方がいいか分からない等、小さなことでも大丈夫です!お問い合わせからお聞きください。専門知識を持った理学療法士がお答えいたします!!